『南方郵便機』の解読(その4)
『南方郵便機』の解読
第2部第2章(ジュヌヴィエーヴの夫エルラン)
彼女はベルニスには、こんりんざい夫のエルランの話をしなかったのに、その夜にかぎって、「退屈な夕食会なの、ジャック、人間ばかり多くて。私たちといっしょに夕食をしてちょうだい。そうすれば、私もひとりぼっちと思う寂しさがまぎれるわ!」と頼んだ。
ジュヌヴィエーヴはベルニスではなく、政治好きのエルランと結婚した。
ジュヌヴィエーヴは物音を忍ばせて、自分の王国で元どおりに片づけるのだった。いっぽうベルニスのほうは、自分を愛してくれた囚われの少女が彼女自身の中に遠く去ってしまって、しっかり守られているのだと、そんなことを感じていた……。
ところが、事物がある日のこと、反旗をひるがえしたのである。
第2部第3章(子供の病気)
「眠らせてよ!」
「ばかをいえ! 起きるのだ。子どもが息苦しそうにしているぞ」
眠気も吹っ飛んだ彼女は、ベッドのところに駆けつけた。子どもは眠っていた。熱のために上気して呼吸もはやいが、静かだ。まだ完全に眠りからさめきらないままに、ジュヌヴィエーヴは引き船のえんえんたる気息を思い描いていた。「一通りじゃないわ!」こんな状態が三日間も続いていたのだ! すっかり思考力を失った彼女は、病児の上にかがみこんでいた。
「どうして、この子の呼吸が苦しそうだなんていったの? どうして、私をどきりとさせたの?……」
彼女の心臓は、まだ激しく動悸を打っていた。
「そう思ったからさ」
三日三晩の徹夜の看病で疲れ切ったジュヌヴィエーヴに医者はちょっとした気晴らしを勧めた。骨董屋で小物を買ってきた彼女に夫エルランは恨みのこもった非難を浴びせ続ける。
第2部第4章(ベルニスの見舞い)
Le soir, quand Bernis vint la voir, elle ne lui parla de rien. On n’avoue pas ces choses-là. Mais elle lui fit raconter des souvenirs de leur commune enfance et de sa vie à lui, là-bas. Et cela parce qu’elle lui confiait une petite fille à consoler et qu’on les console avec des images.
Elle appuyait son front à cette épaule et Bernis crut que Geneviève, tout entière, trouvait là son refuge. Sans doute le croyait-elle aussi. Sans doute ne savaient-ils pas que l’on aventure, sous la caresse, bien peu de soi-même.
日が暮れてからベルニスが会いにきても、彼女はおくびにも出さなかった。ああいうことは、他人の耳に入れるものではないのだ。そのかわり彼女は、二人の共通の幼少時代とか、彼自身のあちらでの生活の思い出を話してくれと、彼にねだった。それというのも、彼女は彼に慰めを必要とする一人の少女をゆだねたからであり、また、少女たちはさまざまなイメージで慰められるからにほかならない。
彼女が自分のひたいを彼の肩にもたせかけていたので、ベルニスはジュヌヴィエーヴが身も心もそこを隠れ家にしているのだと思った。きっと、彼女のほうでもそう思っていたのだ。きっと彼らは、だれでも愛撫されようが、自分自身のごくわずかしか賭けはしないことを知らなかったにちがいない。
第2部第5章(ベルニスへの逃避)
ベルニスが彼女の顔をなでてやる。何かが彼女の記憶によみがえる。
「五年間よ、五年間も……そんなのに、こんなことになるなんて!」彼女はさらに、「あの子のためにさんざんつくしたのに……」と考える。
「ジャック!……ジャック……坊やは死んだの……」
子供が死んだジュヌヴィエーヴはベルニスの部屋に来て一緒に逃げてくれと懇願する。
だしぬけに、彼女ははっとする。
「のこのこ現われるなんて、気違い沙汰ね」
しらじらと明けそめるあけぼのの光に照らされて、わが家ではさんたんたる光景が展開されているなと、彼女はそんなことを感じる。ひやりとする乱れたシーツ。家具の上に放り出されたタオルに、ひっくり返った椅子。彼女はこうしてものがくずれ落ちるのを、早急にくいとめる必要がある。あの肘掛椅子を大急ぎで元の場所に戻さなければならないし、あの花瓶やあの本も。彼女は生活を取り巻くものを元どおりの姿にするために、いたずらに精根を使い果たさなければならないのだ。
第2部第6章(葬儀)
ベルニスが彼女を腕に抱きしめると、ジュヌヴィエーヴはわずかに頭をのけぞらせて、その目が涙で光る。ベルニスが腕にしっかり抱いて放さないのは、涙にむせぶあの少女にほかならぬのだ。
ユービ岬にて、……日 ベルニス、なあきみ、きょうは郵便機が着く日だ。郵便機はシズネロスを発った。まもなくここを通るから、きみにこのいくつかの苦情を伝えるだろう。
あの慣習といわずしきたりといわず法律といわず、きみが必要性を感じないあらゆるもの、きみが逃げだしてきたもののすべて……それが人生のわく組みになるのさ。実際に存在するためには、自分のまわりに永続性のある現実が必要なのだ。もっとも、不条理だとか不当だといったところで、そんなものは単なる言葉にすぎない。きみがジュヌヴィエーヴを連れ去ったら、彼女はもうジュヌヴィエーヴではなくなるだろう。
第2部第7章(ジャックとの再出発に向けて)
「そばにきてちょうだい、ジャック、現実に存在するのはあなただけよ……」 長椅子を照らすこの薄明かり、一人暮らしの男の部屋の壁紙。壁に掛かっているモロッコ製のあの壁掛け。こういったものはすべて、五分間で取りつけたり、取り払うことができる。
彼女は今夜、官能の喜びにふけりながらこの弱々しい肩を、このもろい隠れ家を見つけだして、動物が死ぬときのように、そこに顔を埋めるのだろう。
第2部第8章(パリへの逃避行)
年老いた女中がかいがいしく世話を焼いてくれた。「さあどうぞ、奥さん。お気の毒に。がたがた震えていらっしゃるし、顔も真っ青だわ。湯たんぽをいれてあげましょう。十四号室で、大きないい部屋ですよ……だんなさま、宿帳に記入していただけますか?」汚れたペン軸を指にはさんだとき、彼は二人の性がちがうことに気がついた。ジュヌヴィエーヴのことで召使いたちが気を使うことになるぞと思った。「ぼくのせいだ。つや消しだね」こんどもまた、彼女が助け船を出した。「愛人同士にしたら」と彼女はいった。「いきじゃない?」
彼女は眠っていた。愛の営みなど、彼の念頭にはなかった。そのくせ、おかしなことを夢見ていた。ぼんやりした追憶である。ランプの炎。急いで、ランプに油を注ぎ足さなければならない。それにしても、吹きつける強い風から炎を守る必要もある。
それにしても、とりわけあの無欲は始末が悪い。彼にすれば、彼女が財産の亡者ででもあってほしいくらいだった。物欲に悩み、物欲に心を動かされて、子どもさながらに物欲がみたされるのを求める女であってほしいくらいだ。そうなれば、彼も貧しいことはともかくとして、彼女にいくらでも恵んでやれたはずである。ところが、彼は何もほしがらないこの少女の前で、あわれにもひざまずくばかりだった。
第2部第9章(ホテル)
彼女は相手に、
「私を放さないで!」と叫びたいくらいだ。愛の腕は人間の現在も過去も未来ももろともに、人間をすっぽりと包み、愛の腕が人間を一所に集める……。
「いや。かまわないで」 彼女は起きあがる。
第2部第10章(フォンテーヌブロー)
フォンテーヌブローの近くで、彼女はのどの渇きを覚えた。景色の細かい点の一つ一つに、見覚えがあった。それらは、悠然と構えていた。たのもしげだった。これも必然的なわく組みで、夜明けとともに浮かびでてくるのだった。
ある安レストランで、二人はミルクを注文した。急いだところで、どうなるというのだ? 彼女はミルクをちびりちびり飲んだ。急いだところで、どうなるというのだ? いままでに起きたことはすべて、必然的ななりゆきだったのだ。相変わらず、あの必然性のイメージがつきまとう。
彼女は優しかった。数々のことで、彼にたいする感謝の念に燃えていたのだ。二人の関係はきのうまでとはくらべものにならないほど、なんの煩いもなかった。彼女はにっこりすると、戸口で餌をあさる一羽の鳥を指さした。彼には、彼女の顔がまるきりちがって見えた。こんな顔をどこで見たのだろう?
第2部第11章(ノートルダム寺院 神とは?)
ノートル=ダム寺院のそばを通りかかったので、彼は中に入ってみたところ、ぎっしりつめかけた人の群れにびっくり仰天して、一本の柱のかげに身を寄せた。いったい、どうしてこんなところにきてしまったのだろう。彼は、われながらそれが不思議だった。どう考えても、彼がここに来てしまったのは、ここでは一瞬一瞬が何かに導いてくれるからだった。そとに出れば、一瞬一瞬経っても、もうなんにもならなかった。理由は、「そとにいれば、一瞬一瞬経っても、もうなんにもならない」というところにある。彼は自分を見極める必要も感じて、思考の規律ならなんでもというつもりで、信仰に身をささげた。そして、「おれの気持を表現し、おれを一つにする言葉を突き止めたら、おれにとっては、それがほんものだろう」と考えた。それから、「もっとも、そんなものを信じはしないだろう」と、ものうげに言いそえた。
「父なる神の名において……」
ベルニスは、「ひどい絶望といったら! どこに信仰があるのか? おれが聞いたのは信仰の言葉ではなくて、まるでどうにもならない叫び声なのだ」と思った。
それにしても、このたそがれときたら…… あまりにも芝居がかりなこの背景の幕は、いままでに諸帝政の滅亡とか、敗戦の夕暮れとか、うたかたの恋の大詰めに使われたことがあるし、これからは、べつの芝居にも使われるだろう。どんな劇が演じられるものやら見当もつかぬところから、夕暮れが静かで、生がだらだら長引くと気のもめる背景の幕だ。ああ! これほどまでに人間臭い心配から彼を救いだすための何かが……。
アーク燈がいっせいに輝いた。
第2部第12章(肉体への逃避)
彼の目の前にあるこの背中は神秘的で、湖面を思わせるようになめらかだ。ところが、かすかにしぐさを見せるとか、考えごとをするとか、あるいは身を震わせるだけで、その背中に影の大きなうねりが伝わった。ベルニスは、「この下にうごめいているえたいの知れないものがすべて、おれには必要なのだ」と考えた。 踊り子たちは砂の上にいくつかの謎を描いて、こんどはそれを消し終わると、おじぎをした。ベルニスは、いちばん身のこなしが軽やかな女に合図を送った。
はやくも彼の心の中では、すっかり熱がさめていた。彼は、「きみはおれのほしいものは、何一つとして恵むことができないのだ」と思った。そのくせ、孤独がひしひしと胸にこたえたので、彼には彼女が必要だった。
第2部第13章(決別)
片手で、彼はこの女のわき腹にさわってみる。そこだと、肉も無防備なのだ。女、それこそ生きた肉のうちでもいちばんむきだしで、この上もなくやわらかな光に輝く肉体である。彼は女を生き生きとさせ、太陽のように、また内面の気候のように女を温めるこの神秘的な生命に思いをいたす。ベルニスは彼女が優しいとか美人だとは思わないで、なま温かだと思うばかりだ。動物を思わせるようななま温かさである。生命が通っているのだ。そしてこの心臓もつねに鼓動を続け、彼の泉とはべつの泉がこの身体の中に閉じ込められている。
彼は、自分の中で数秒間はばたきをしたあの官能の快楽のことを思い浮かべる。羽ばたきをして死んでゆく、あの気違い鳥のようなものだ。さていまや……。きちんと片づいたこのサロンは、プラットホームを彷彿とさせるものがある。ベルニスはパリで、特急列車の発車時間までむなしい時間を過ごした。ひたいを窓ガラスにあてて、彼は人群れが引きあげてゆくのを見つめている。この人の流れに、置き去りにされるのだ。各人が仕事をかかえて、道を急ぐ。人生の筋書が始まっても、それは彼とは関係なしに結末に導かれるのだろう。通りすがりのあの女も、ほんの十歩も進めば、時間のそとにでてしまう。この人群れは涙と笑いでわれわれの糧となる生きた素材だったのに、いまや、死んだ人たちの群れと変わりがないのだ。
いまや、窓いっぱいに空が震えている。おお、男の欲情で踏みにじられもてあそばれた、愛の営みのあとの女。冷たい星の間に、ぽいと放り投げられたのだ。心の景色がさっさと変わる……情欲も経たし、情愛も経て、火の河も経てきた。いまやけがれなく冷え切って、肉体からも解放された上で、船の舳に立って海に乗りだしてゆく。
第2部第14章(パリからの帰還)
きちんと片づいたこのサロンは、プラットホームを彷彿とさせるものがある。ベルニスはパリで、特急列車の発車時間までむなしい時間を過ごした。ひたいを窓ガラスにあてて、彼は人群れが引きあげてゆくのを見つめている。この人の流れに、置き去りにされるのだ。各人が仕事をかかえて、道を急ぐ。人生の筋書が始まっても、それは彼とは関係なしに結末に導かれるのだろう。通りすがりのあの女も、ほんの十歩も進めば、時間のそとにでてしまう。この人群れは涙と笑いでわれわれの糧となる生きた素材だったのに、いまや、死んだ人たちの群れと変わりがないのだ。
(この項、続く)
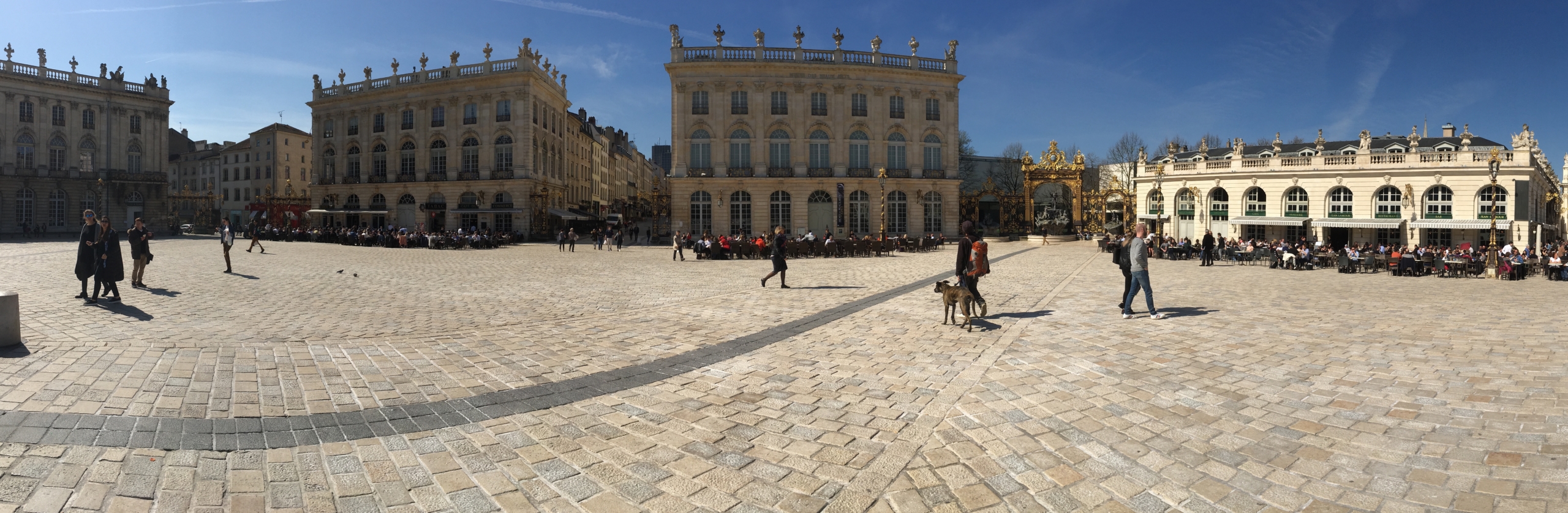
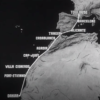

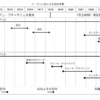



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません