「サルトルによるフローベールの生涯の再構築」その2「神経症計画」 planning névrotiqueについて

はじめに
この項はYoung-Rae Ji氏の論文La reconstruction sartrienne de la vie de Flaubert(サルトルによるフロベールの人生の再構築)の後半部分の翻訳である。1当初、この論文を批判的に論じようと思ったが、論旨明快で率直なこの論文をそのまま日本語に翻訳して日本人の読者に提供するほうが有意味だと考えたからである。前の投稿がこの論文の前半を論じているので、そちらも参考にしていただけば幸いである。
「神経症計画」planning névrotique について(翻訳)
では、今度は、次男という条件、したがってより低い条件を与えられたギュスターヴが、自分を取り巻くこれらすべての悪を「できるだけ苦しむことがないように自分自身を深く組織化する」(IDF, t. I, p. 1862)ことを決定する「神経症計画」を検討してみよう。家族によって条件づけられ、受動性として構成され、言葉が「ひどくねじれた」(IDF、I、p.24)ギュスターヴは、彼の人生をかなりひどい状態から始めた。 しかし周囲が作った自分をフローベールは人格形成のゆっくりした動きで克服しようとする。それはサルトルによれば、フローベールの「文学的プロジェクト」と密接に結びついている彼の「神経症計画」、または「神経症プロジェクト」 (IDF, t. II, p. 1930)によって組織されている。
活動的で実用的なフローベール家の宇宙から排除されて、ギュスターヴは彼を無力の刑に処した家族の判決を受け入れ、他人によって行われた評決を彼の神経症的戦略の口実に変換する。それはついにはある状態を受け入れ、静かに文学に専念する権利を彼に与える。 17歳の時にギュスターヴが職業を選ぶように要請されたとき、彼は自分の「ブルジョア存在」を発見し(IDF, t. II, p. 1485)て拒否するが、受動的な性格が彼に反乱を禁じる。明らかな従順さを見せながら、彼はそれから神経症を発展させ、その壮大な効果を1844年1月のある1日に見せることになる。フローベールが1817年から1822年の間に経験したこの危機をサルトルは「psychosomatique(心身医学)」と呼ぶ。サルトルが「前神経症」というタイトルで300ページ以上を費やす心身医学的危機のこの時期に、ギュスターヴは彼の「目的論的意図」(IDF, t. II, p. 1827)をもって神経症を準備し、「緊急事態への即効的で否定的かつ戦術的な対応として」1844年のポン=レヴェックの転倒として発症することになる (IDF, t. II, p. 1779)。ポン・レヴェックのこの危機から、ギュスターヴは静かにクロワッセに撤退し、そこで彼は彼が理想に達することを可能にする文体を見つけるために、宗教的緊張を維持しながら自主的な隔離の人生を送る。彼は〈美〉を必死に探し求めることによって、書くという苦痛な仕事に苦しむ殉教者になるだろう。
これがサルトル版フローベールの「神経症的計画」で、このなかでサルトルは「書くことが神経症になり神経症が文学になるまで、芸術的プロジェクトと神経症的プロジェクトを相互に条件付ける弁証法的な動き」を示している (IDF, t. II, p. 1930).。 それでもこのサルトル説は何よりもフローベールの病の性質に関するかなり疑わしい診断に基づいている。サルトルはギュスターヴ・フローベールは癲癇ではなく神経症を患っていると確信しているからだ。
神経症? 癲癇? この病気の性質について多くのことが書かれている。しかし、この2つの名称にはどのような違いがあるか? 一世紀以上前に亡くなった作家の病気の決定はそれほど重要なのだろうか。そう、少なくともサルトルにとっては。なぜなら、この勝負の賭け金がサルトル哲学の本質的なテーマ、個人の自由に他ならないからだ。[efn_noteefn_note]Voir IDF, t. II, p. 2150 : « La maladie de Gustave exprime dans sa plénitude ce qu’il faut bien appeler sa liberté.»『家の馬鹿息子』第4巻、395ページ。「ギュスターヴの病は彼の自由と呼ぶべきものを余す所なく表現している。」[/efn_note]. 神経症とは何か? その定義はそれほど単純ではない。 例として、Jean LaplancheとJean-Baptiste Pontalisの『精神分析の語彙』で、精神科の教科書から抜粋されたこの定義の試論は次のようになっている。「 不安に対する防御を示す行動、感情、または思考の不調であり、この内的葛藤に関して妥協を構成し、その当人はその神経症的立ち位置から特定の利益を引き出す3」
「神経系の損傷の存在を推定するのに十分な理由がある4」疾患の一つである「癲癇」とは反対に、「神経症」は病理学的には「神経系の器質的な損傷がないにも関わらず、臓器レベルにおける身体的な障害によって出現する神経系の機能障害5」として定義される 。もしフローベールが癲癇(器質性欠陥によって引き起こされる病気)に苦しんでいるならば、この病気のすべての結果、彼の人生と彼の作品は、偶然の産物に過ぎない。すなわち、サルトルの視点では人間の自由の余地はほとんどない。この診断は、人間はもはや自分自身の運命の主人ではないという有機的決定論の主張につながる。1844年1月の出来事が癲癇の結果であったならば、フローベールの先史時代と彼の初期の作品の全体の分析は崩壊し、客観的精神と個人の間の弁証法的な運動というサルトルの議論の全体がその基盤を失う。
サルトルにとって、ポン=レヴェックの危機は意図の成果であり人生の選択の結果でなければならない。彼によれば、フローベールはそれゆえ、彼がそうなると自ら決めねばならなかったこの種の作家になるために病気を選んだ。なぜなら、この「ヒステリックなアンガージュマン」 (IDF, t. II, p. 1864)は、彼をして自分の神経症計画を達成することを可能にし、そのようにして、「客観的神経症」および当時に固有の計画との関係において、自分の病気に押し付けた象徴的改心と同じく意図的幽閉も正当化することを可能にする。これらすべての主張を支持するために、サルトルは、フローベールが癲癇ではなく神経症であることをすべての犠牲を払って証明しなければならない。「非常に説得力のある論証」 (IDF, t. II, p. 1796) によるルネ・デュメニル博士の診断は彼の立論のためのよい証拠を与える。それでも、サルトルが本を書いた時点では、ほとんどのフローベール研究者はむしろ癲癇を選択している。
フローベールの神経疾患の本質について、1860年から大変な議論になった。フローベールの同時代人、マキシム・デュ・カン、アンリ・モニエ、ゴンクール兄弟、そしてジョルジュ・プシェ博士はすでに癲癇と診断していた6。しかし、1905年頃にフローベールの病について医学論文を書いたルネ・デュメニルは、フローベールの親戚の証言と彼の手紙を再検討し、フローベールが神経症だけで苦しんだことを証明しようとした。彼の分析の主な根拠は、とりわけデュ・カンが『文学回想録』7、そしてフローベールの手紙の抜粋8という形の彼自身による危機の説明である。「フローベールの病気と死」と題された記事の中で、デュメニル博士は『文学回想録』の出版以来、一般的に採用されている意見、癲癇の診断を除外しようと試み、今度は彼が神経症の診断を公式にした。以下が彼の記事からの抜粋である。
今読んだことは、本態癲癇、聖なる病には当てはまらない。そして、これがこの診断を正式に排除している理由である[…]。危機の間に括約筋の弛緩、舌の噛みつきはない。これらの症状が存在していたら、デュ・カンは喜んでそれを報告していただろう。 […]しかし、それよりも、最初の危機が発生した22歳という年齢は、ほとんど常に小児期から現れる病気である本態癲癇をアプリオリに遠ざける。最後に、癲癇患者はまるで「彼が棺の中で生きながら眠っているかのように」自分のベッドに横たわるため、自分が倒れる場所を選ぶ時間などない。そして後に、フローベールが自分の危機について話すとき、フローベール本人は同じくらい正確である。「私は話すことができなかったときでさえ、私はいつも気づいていました」と彼はルイーズ・コレに書いた。「意識は最後まであったし、さもなければ苦しみは無かっただろう」自分の危機に気づき、その報告を公開できるような癲癇がどこにあるだろうか。
René Dumesnil, Gustave Flaubert, l’homme et l’œuvre, éd. citée, Appendice A, p. 487-489. Nous soulignons.
これが、サルトルが完全に採用した意見である。 サルトルがこの結論に達するために、最初から神経症の仮説で始めていなかったとしたら、フローベールの病の性質について長い間検討した後にようやく神経症を選んだのであろう。 しかしながら、現代医学はこの診断と一致しない。1962年に、ガレラン博士はガレ博士の主張についての報告を発表したが、そこでデュメニル博士の議論を逐一反論しながらフローベールの病気を確定するために癲癇を提案した。
ギャレット博士の結論は疑いなく、癲癇であるとして反論の余地がない。 […] デュメニル博士は次のような口実で癲癇を否定している。
1.前兆(aura)があまりに長すぎ、また癲癇は彼が倒れる場所を選ばない。ところが、フローベールがけいれんの段階に入ろうとしていたちょうどその時、長椅子に横たわることになった。それは間違いである、と若い弟子が先輩に反論する。われわれは前駆症状prodromesと前兆auraという2つの異なる要素を混同してはならない。さて、差し迫った危機の数日前には、多くの癲癇患者に警告が表示されることがある。フローベールは数分の自由な間隔を持っていて、それはソファに行くのに十分であった。
2.彼は自分の危機の記憶をもっている。別の誤解釈である。彼は前兆を覚えていて、それは正常だが、危機の記憶ではない。 […]
3.癲癇は22歳から始まらない。これは間違っている。それを決定する原因によって、この病気は任意の年齢で始まる。
4.危機の間に尿失禁はなかった、さもなければデュ・カンは喜び勇んでそれを言っただろうからだ。これは、われわれが見たように、精査に耐えられない純粋に根拠のない主張である。
Docteur Galerant, « Quel diagnostic aurions-nous fait si nous avions soigné Gustave Flaubert ? 「もしわれわれがギュスターヴ・フローベールを看病したとしたら、どのように診断するだろうか– ガレット医師の仕事の分析のためのノート」
ギャレット博士とギャラン博士は、デュ・カンの証言の信憑性について疑問を投げかけて自分たちの主張を正当化している。デュ・カンが「疑わしい証人であり、まず日付と場所を欺くことから始める人」であることは事実であるが(IDF、II、1784)、彼の証言は二人の博士によれば、技術的には「疑いのかけようもない9」ものである。癲癇。 これはイギリス医学の結論でもある。 シラキュース大学医学部の脳神経外科の教授であるアーサー・エッカー博士は、独自にフローベールの症例の分析を行って、同様の結論に達した10。 今日の医学のこれらの確認以来、癲癇の診断は一般的にフローベール批評家の間で受け入れられている11。
それで、サルトルはこれらすべてを知らなかったのか? たぶんそんなことはない。しかし、このような癲癇の診断は、フローベールの病を単なる事故と見なしているため、彼には意味がない。この種の器質的決定論は、例えば、Philippe Bonnefisによる記事が示しているように、「Flaubertを照らし、彼に華々しく訪れた癲癇は神聖な病、祝典、奉献であった12」と宣言して、フローベールの作品全体を、癲癇の不本意な結果と見なして、フローベールによって創られた特異な宇宙を彼の物理的欠陥の単純な偶然の結果に還元することにつながるだけだ。
器質的な起源であろうとなかろうと、サルトルにとって、フローベールの病は「本来の意図に応じて組織された。ポン・レヴェックにおけるその電撃的な構造は偶然の事実ではなく、意味を与えられた必然性である 」(IDF、II、1796)。サルトルはそれの中に、自分の困難な実存の中に再び飛び込むことを可能にする目的性、「積極的戦略」(IDF、II、1933)を見る。最初に、世界に投げ込まれ、環境の「実践的惰性態」に襲われた人間存在がいる。この人間は、自分の存在の最深部における自由な存在として、自分の病気によって世界で自分自身が決定的に受動的になることを選んだ。そしてギュスターヴを作家ギュスターヴ・フローベールにするのは、この自主的な選択となるだろう。要するに、1844年のフローベールの危機は「彼の不幸な青年時代の数学的帰結」であり、「彼の天才はポン・レヴェックでの彼の偽死の単なる数学的帰結であり、外化した絶望にすぎない」(IDF II、pp。2024)。このレベルでは、サルトルのフローベールに関する伝記的エッセイは小説の世界にあると言える。もちろん、サルトルにとって、この神経症の仮説もまた選択である。フローベールはたぶん癲癇であった、そしてサルトルが主張したこととは反対に、癲癇は起源にヒステリー症を持っていないだろう。それがどうだというのだ。サルトルの興味を引くのは、フローベールの人生の歴史的な正確さではなく、特に真実に、「普遍的独自」の完全な理解、ギュスターヴ・フローベールという名前の個人の首尾一貫性に到達するための方法論的研究である。
このように、われわれは『家の馬鹿息子』をむしろ実証主義的な観点から検討したところだ。そして、サルトル的「フローベール」についてのフローベール派の懐疑的な見方は、理由がないわけではないことを確認した。サルトルが『家の馬鹿息子』の最初の2巻の出版直後に言ったように、彼が自分の本で描いたものはフローベールそのものではなく、「フローベールはこういう人間だったという自分の想像13」だという。これによって、この本は、歴史的調査というよりもむしろ小説的想像力をわれわれに要求することによって、学術的批判より純文学批判にさらされることになった。しかし、『家の馬鹿息子』を小説または偽装伝記として読むことによって、その価値をより正確に理解できるようになった。そして、『家の馬鹿息子』が小説から来ているのか、あるいは(自叙)伝記から来ているのかという疑問は、特に解釈学の立場から解明される神話と歴史との関係に関する一般的な議論によって解明されるであろう。2つの物語を区別するのはいつでも必ずしも容易ではないようである。フィクションが現実を探るための適切な方法ではあり得ないかどうかという問いもますます求められている。一言で言えば、たとえ『家の馬鹿息子』がフローベール派の学者にとってあまり役に立つ本ではないということが本当であっても、J. Bruneauが言うように、この本は「誰にとっても非常に重要14」であることは間違いないのだ。
(この項終わり)
- 原文は上のリンクにPDFがダウンロードできるので、興味ある方はどうぞ
- IDFはL’Idiot de la familleの略、t.Iは第一巻の略
- J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, 1967, p. 270.
- Ibid., p. 268. Nous soulignons.強調は私。
- Trésor de la langue française, Gallimard, 1986. Nous soulignons.
- Voir Jean Bruneau, Les Débuts littéraires de Gustave Flaubert, Armand Colin, 1962, p. 360, note 10.
- Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, Aubier, 1994, p. 199-203.
- Principalement, la lettre à Ernest Chevalier du 1er février 1844 et la lettre à Louise Colet du 2 septembre 1853.
- Docteur Galérant, « Flaubert vu par les médecins d’aujourd’hui »「今日の医療から見たフローベール」, Europe, septembre-novembre 1969, p.108.
- Voir Benjamin F. Bart, Flaubert, New York, Syracuse University Press, 1967, p. 752-753.
- Voir Jean Bruneau, « Notes et variantes », dans Flaubert, Correspondance I (1830-1851), Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 943-944, et Marthe Robert, En haine du roman, Balland, « Le Livre de Poche », 1982, p. 57-68.
- Ph. Bonnefis, « Aura epileptica », Magazine littéraire, n° 250, février 1988, p. 41.
- J.-P. Sartre, Situations X, éd. citée, p. 114.
- Jean Bruneau, « L’intervention », Langages de Flaubert, éd. citée, p. 230.
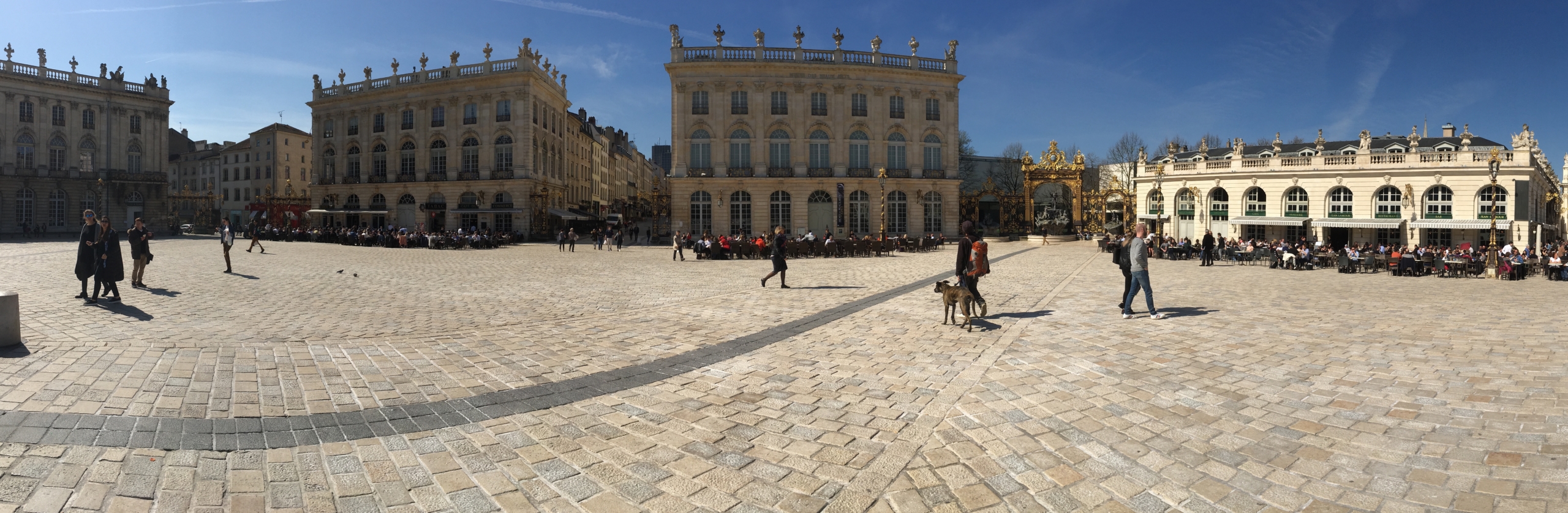

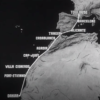





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません