『南方郵便機』の解読(5/5)
『南方郵便機』の解読
第3部第1章(タンジェ上空からカサブランカに着陸)
舞台はすっかり変わってベレニスが操縦する飛行機の行方に移る。トゥールーズ、バルセロナはもちろん、さきほど郵便機を発たせた後のアリカンテも格納庫も閉めて仕事納めである。これから郵便機を迎えるカサブランカから先の中継地はやきもきしながら郵便機の経過を見守っている。
ツールーズもバルセローナもアリカンテも、郵便機を早々に飛び立たせたあと、小道具を片づけ、飛行機も格納して格納庫を閉めていた。マラガでは、郵便機が通るのは昼間に予定されていたから、照明燈を用意する必要はなかった。しかも、着陸はしないだろう。おそらくずいぶん低空を、タンジェの方向にそのまま飛行し続けるだろう。きょうもまた、アフリカ海岸は視界におさめずに羅針盤だけをたよりに、高度二十メートルで海峡を越えなければならないかもしれぬ。強い西風が海を掘り起こすようだった。波がくだけて、白い色を見せていた。投錨ちゅうのどの船も舳を風に向けて、沖合にいるときのようにそのリヴェットのすべてを動員して、激しく揺れながらふんばっていた。東ではイギリス岩山〔ジブラルタル岩山〕のところに低気圧が発生して、雨がどしゃ降りだった。西のほうは、雲が一段と高くなっていた。海の向こう側では、タンジェが町も洗い流すほどの豪雨の下で煙っていた。水平線のかなたに、おびただしい積雲の山。ところが、ララーシュのあたりは、空も澄んでいた。

カサブランカは、雲一つない空の下で呼吸していた。点々と帆船が浮かんでいるので、港だとわかったが、それがまるで戦闘のあとのようだった。あらしでさんざんに荒らされた海上に見えるのは、扇形にひろがる長い規則的な航跡ばかりだった。野原は夕陽を受けて、さらに輪をかけてあざやかな緑色を帯び、水のように深く見えた。ここかしこ、町はまだ濡れたところが輝いていた。発電所の小屋の中で、電気技師たちが手持ちぶたさに待機していた。アガディルの電気技師たちは、まだ四時間も間があるので、町にでて夕食の最中だった。ポール=エチエンヌ、サン=ルイおよびダカールの電気技師たちのほうは、まだ眠っていてもかまわなかった。
(中略)
アガディルでは、狐につままれたようだった。計算の上では、郵便機はとうにカサブランカを出発したはずである。念には念を入れて、みんなが郵便機を見張っていた。
(中略)
それでも、世界から孤立したユービで、われわれは一隻の船を思わせるように、S・O・S を発信し続けていた。
《郵便機ノ消息ヲ連絡サレタシ 連絡ヲ乞ウ……》
シズネロスは同じことをくどくど聞いてこちらをいらいらさせるばかりなので、われわれはもうシズネロスには応答しなかった。
(中略)
二十時五十分に、すべての緊張がほぐれた。カサブランカとアガディルとの間で、電話連絡がついたのだ。われわれの無電のほうも、ようやく波長が合った。カサブランカが発信すると、その一語一語がダカールまでおうむ返しに伝達された。
《郵便機二十二時ニ アガディルニ向ケテ出発ノ予定》
《ダカールヨリ ユービヘ 郵便機零時三十分ニ アガディルニ到着ノ予定 貴地ニ向ケテ飛行ヲ続ケサセルモ 可ナリヤ?》
《ユービヨリ アガディルヘ コチラハ霧 日ノ出ヲ待テ》
《ユービヨリ シズネロス、ポール=エチエンヌ、ダカールヘ 郵便機アガディルデ夜ヲスゴス予定》
パイロットはカサブランカで飛行記録にサインすると、ランプの光の下で目をぱちくりさせていた。
(中略)
彼は十時間も風にマッサージされたところから、顔が赤くなっていた。彼の髪の毛から、汗がしたたり落ちていた。
この流れはなかなかに複雑で、読み手の混乱を招く。トゥールーズ―バルセロナ―アリカンテのヨーロッパは舞台袖に引っ込んで、タンジェ―カサブランカーアガディル―キャップジュビーシズネロスーポール=エティエンヌーダカールのアフリカ側が飛行機の進路を求めて混乱を極めている。語り手の<われわれ>は、どうやらユービ(キャップジュビ)にいるらしいが、中継地はどこも色めき立って無線電報やら電話やらで空中戦を交わしているのがわかる。そんな心配をよそに、パイロットのベルニスはカサブランカに無事降り立ったようである。第1部第3章でアリカンテを出発したのが、おおよそ12時頃とすると、「十時間も風にマッサージされた」というわけだから22時頃になっていただろう。
飛行場主任はドアをちょこっとあけて、タバコを暗闇の中に投げ捨てた。
「ほう! 見えるぞ……」
「何が?」
「星だよ」
パイロットはしびれをきらした。
「あなたの星なんてどうでもいいですよ。三つ見えますがね。あなたが私を行かせるその先は、火星ではなくてアガディルなんですよ」
「一時間後には月もでる」「月ですって……月とはまた……」
この月の話で、彼のくやしさがなおさらつのった。それじゃ、自分は夜間飛行のために月の出を待っていたのか? いまだに練習生なのか?
こういうやり取りはあったものの、カサブランカの飛行場主任は非情にも出発を命じ、パイロットも黙って受け入れた。正確にはわからないがおよそ23時頃だっただろう、ベルニスは出発する。
パイロットはにっこりして立ちあがると、新しい空気を胸いっぱいに吸い込んだ。「ああ! さようなら」
こんなふうに、ときおりフィルムが中断するものだ。何もかもぴたりと動かなくなって、一秒一秒が人事不省におちいったときのようにいやが上にも大事になり、そのうちにまた生気がよみがえる。
(中略)
彼は羅針盤で針路を修正した。沖合の右方向に流されていると、奇妙にもそんなふうに感じていたのだ。自分の影におびえる牝馬と同じで、まるで左手の山々が、実際に彼のほうにのしかかとでもいわぬばかりだった。
「どうやら、きっと雨だぞ」
彼が片手をだすと、その手を雨しずくが激しくたたいた。
「二十分で海岸に達して、そのあとは平野だから、危険も減るだろう……」彼は羅針盤で針路を修正した。沖合の右方向に流されていると、奇妙にもそんなふうに感じていたのだ。自分の影におびえる牝馬と同じで、まるで左手の山々が、実際に彼のほうにのしかかとでもいわぬばかりだった。
ところが降ってわいたように、すばらしい雲の切れ間だ! 空は雲がすっかり吹きはらわれて、空一面の星がま新しくきれいに洗われていた。月だ……月、ありがたいぞ、最高のランプだ! アガディルの飛行場が、ネオンサインのように三回光った。
「あそこの光なんぞ、くそくらえだ! 月が出ているのだからな……!」
第3部第2章(遭難か?)
夜明けとともに、ユービ岬では幕があがったが、舞台は私の目にはがらんとしていた。影もなければ背景もない道具立て。いつも同じ位置にあるあの砂丘、あのスペイン砦、この砂漠。穏やかな天気のときですら、牧場や海に光彩を添えるあのかすかな動きが欠けていた。ゆっくりした足どりの隊商を組む遊牧民たちは、砂粒の変化を見て、日が暮れてから周りが処女地のところにテントを張るのだった。私だって、ほんのわずかでも動けば、砂漠の果てしないひろがりを感じ取れたかもしれないが、まるきり変わらないこんな景色が相手では、着色石版刷りと同じで、思考もかぎられてしまうのだった。
(中略)
« Parti à cinq heures d’Agadir, tu devrais avoir atterri. »
– Parti à cinq heures d’Agadir, il devrait avoir atterri.
– Oui mon vieux, oui… mais c’est du vent Sud-Est.
《きみは五時にアガディルを出発したのだから、とうに着陸していたはずだ》
「彼は五時にアガディルを出発したのだから、とうに着陸していたはずだ」
「そうにはちがいない、きみ、そうなんだ……しかし、南東の風が吹いているし」
語り手の<私>は、ユービ岬(キャップジュビ)にいる。カサブランカを23時に発って夜間飛行をした郵便機は4時頃にはアガディルに到着し、5時にはユービに向けて飛び立っているはずだ。だからそろそろこちらについてもいいころではないか、話はこういうことになっている。1行目のtuは語り手からベルニスへの心の中の呼びかけで、2行目は通信士に話しかけている。3行目は通信士から語り手への返事である。
On pense vaguement au drame. Un courrier en panne, ce n’est rien qu’une attente qui se prolonge, une discussion qui s’énerve un peu, qui dégénère. Puis le temps qui devient trop large et que l’on remplit mal par de petits gestes, des mots sans suite…
Et soudain, c’est un coup de poing sur la table. Un « Bon Dieu ! Dix heures… » qui dresse des hommes, c’est un camarade chez les Maures.
大事になったらという思いが、漠として頭をかすめる。郵便機が一機故障したのなら、待機が長引いて、議論もいくぶん殺気を帯びながらひどくなるだけの話だ。そのうちに、時間がむやみに長くなるばかりで、こせこせした所作や支離滅裂な言葉ではその時間のつぶしようもない……。
だしぬけに、テーブルをこぶしでたたく者がある。「くそっ! もう十時だ……」という言葉を潮に、一座の人たちがさっと立ちあがる。僚友が一人、マウル人にとらわれの身になったのだ。
長塚さんはうまく訳してくれる。時間は10時だったんだ。5時にアガディルを発った郵便機は5時間語にはとっくにユービに到着して不思議はない。それがいまだに音沙汰がないのはきっと不時着してマウル人の捕虜になったに違いないということなのだ。そこから情報収集の格闘が始まる。
Agadir est toujours muet. Nous guettons maintenant sa voix. S’il cause avec un autre poste, nous nous mêlerons au discours.
Je m’assieds. Par désœuvrement, je m’empare d’un écouteur et tombe dans une volière pleine d’un tumulte d’oiseaux.
Longues, brèves, trilles trop rapides, je déchiffre mal ce langage, mais combien de voix révélées dans un ciel que je croyais désert.
Trois postes parlaient. L’un se tait, un autre entre en danse.
– Ça ? Bordeaux sur l’automatique.
Roulade aiguë, pressée, lointaine. Une voix plus grave, plus lente : – Et ça ?
– Dakar
Un timbre désolé. La voix se tait, reprend, se tait encore et recommence.
… Barcelone qui appelle Londres et Londres qui ne répond pas.
Sainte-Assise, quelque part, très loin, conte en sourdine quelque chose.
Quel rendez-vous au Sahara! Toute l’Europe rassemblée, capitales aux voix d’oiseaux qui échangent des confidences.
Un roulement proche vient de retentir. L’interrupteur plonge les voix dans le silence.– C’était Agadir ?
– Agadir.
L’opérateur, les yeux toujours fixés, j’ignore pourquoi, sur la pendule, lance des appels.
– Il a entendu ?
– Non. Mais il parle à Casablanca, on va savoir.

無線通信士
アガディルは相変わらず応答なしだ。われわれはいまや、その声をとらえようと耳を澄ます。アガディルが他の局と交信中なら、われわれもその話に割り込もう。
私は腰をおろす。それから暇つぶしに、レシーバーを取りあげると、小鳥のざわめきがあふれる大きな鳥籠の中に落ち込むようだ。
長く、短く、いやにはやいトリルで、私にはこの言語が解読できないが、私が何一つないと思っていた空中に、どれほどの声が聞こえたことだろう。
三つの局が交信していた。一つの局が発信をやめると、べつの局が乗りだしてくる。
「これですか? 自動呼びだしのボルドーです」
鋭くあわただしくて、はるかな旋転。いやさらにもったいぶって、さらにのろのろしたべつの声。
「これは?」
「ダカールです」
悲しげな響き。その声はとぎれてはまた始まり、もう一度とだえてはまた話し始める。
「……バルセローナがロンドンを呼びだしていますが、ロンドンの応答はありません」
サン=タシーズ1がどこかはるかかなたで、声をひそめて何やら話している。
サハラ砂漠で、ランデブーの多いことといったら!
ヨーロッパ全体がそこに集まって、小鳥の声をした各首都が内緒話を交わしている。
近くでガーガー鳴る音が響いた。スイッチをひねると、ほかの声がいっせいにやむ。
「アガディルだったね?」
– Agadir.
L’opérateur, les yeux toujours fixés, j’ignore pourquoi, sur la pendule, lance des appels.
– Il a entendu ?
– Non. Mais il parle à Casablanca, on va savoir.Nous captons en fraude des secrets d’ange. Le crayon hésite, s’abat, cloue une lettre, puis deux, puis dix avec rapidité. Des mots se forment, semblent éclore.
« Note pour Casablanca… »
Salaud ! Ténériffe nous brouille Agadir ! Sa voix énorme remplit les écouteurs. Elle s’interrompt net.
« … terri six heures trente. Reparti à… »
Ténériffe l’intrus nous bouscule encore.
Mais j’en sais assez long. À six heures trente le courrier est retourné sur Agadir. – Et n’a dû repartir qu’à sept heures… Pas en retard.
– Merci !
「アガディルです」
無電技師はなぜともなく相変わらず時計に目をすえたまま、呼び出し音を発信している。
「聞きつけたかね?」
「いいえ。しかし、カサブランカと交信していますから、いまに気がつくでしょう」
われわれは天使の秘密を盗み聞きする。鉛筆が思いまどった末に横に倒れると、一字、二字、十字とつぎつぎにすばやく、しっかり書き留める。いくつかの言葉が組み合わされて、花と開くようだ。
《カサブランカ宛テ通達……》
ちくしょう! テネリフェ2がアガディルを呼ぶわれわれを妨害しているのだ! その破れ鐘のような声が、レシーバーいっぱいに響きわたる。それがぴたりとやむ。
《……陸ハ六時三十分 出発時間ハ……》
テネリフェが割り込んで、またしてもわれわれを混乱させる。
それでも、私にはかなりくわしいことがわかる。六時三十分に、郵便機はアガディルに引き返した――霧のためだろうか?
エンジンの不調か?――ふたたび出発したとしても、せいぜい七時のはずだ……遅れているのではない。
「ありがたい!」

無線通信の実態は私達にはなかなか理解が難しい。無線通信士はモールス信号で送られてくる音声信号を聞き取ってアルファベットに戻して筆記する。それがつながるとようやく単語や文になるのだ。だから、通信士の訓練をしたことがない操縦士がレシーバーでいくらモールス信号を聞いたところでトンツー・ツートンツーの連続で、簡単に解読できるものではない。サン=テグジュペリはその事情を解説しないで提供している。それがサン=テグジュペリの文章の肝なのだろう。
聞き取りにくい無線通信のやりとりから判明した事実は、カサブランカから夜間飛行でアガディルに到着した郵便機は、5時にはアガディルを出発したが悪天候のせいかそのままアガディルに引き返したということらしい。
モールス信号の音声は下のように聞こえる。当然だが、門外漢の私には何も意味がわからない。
第3部第3章(ユービ)
Jacques Bernis, cette fois-ci, avant ton arrivée, je dévoilerai qui tu es. Toi que, depuis hier, les radios situent exactement, qui vas passer ici les vingt minutes réglementaires, pour qui je vais ouvrir une boîte de conserves, déboucher une bouteille de vin, qui ne nous parleras ni de l’amour ni de la mort, d’aucun des vrais problèmes, mais de la direction du vent, de l’état du ciel, de ton moteur. Toi qui vas rire du bon mot d’un mécanicien, gémir sur la chaleur, ressembler à n’importe lequel d’entre nous…
いいかジャック・ベルニス、こんどこそ、きみが着かないうちにきみという人間のベールをはいでおこう。きのうから、無電で正確な位置を知らされていて、いよいよここで規定の二十分間を過ごすきみ、私が罐詰を一個あけ、ぶどう酒のびんをぬいてご馳走しようとするきみ、われわれに愛とか死とか、真実の問題にはこれっぽっちもふれないで、風向きやら空模様やらエンジンのことばかりを話題にするはずのきみ。整備員の冗談に大笑いしたり、暑さに悲鳴をあげたり、われわれのうちのだれとでも似てくるはずのきみ……。
(中略)
アガディルを発ったベルニスと郵便機は無事にユービ岬に到着した。急いで出発したい素振りのベルニスに<私>はジュヌビエーブとのその後の経過を教えろと迫る。
– Laisse-moi partir.
– Tu as cinq minutes. Regarde-moi. Que s’est-il passé avec Geneviève ? Pourquoi souris-tu ?
– Ah ! rien. Tout à l’heure, dans la carlingue, je me suis souvenu d’une vieille chanson. Je me suis senti tout à coup si jeune…
– Et Geneviève ?
– Je ne sais plus. Laisse-moi partir.
– Jacques… réponds-moi… L’as-tu revue ?
– Oui…
– Il hésitait.
– En redescendant sur Toulouse, j’ai fait ce détour pour la voir encore…
Et Jacques Bernis me raconta son aventure.
「出発させてもらいたい」
「まだ五分あるよ。おれを見ろよ。ジュヌヴィエーヴとの間に何があったのだ? なぜ笑うのだ?」
「なあに! なんでもない。ついさっき操縦席で、古い歌を思いだしてね。にわかに、自分がすっかり若返ったように感じたよ……」
「それで、ジュヌヴィエーヴは?」
「その後は知らないね。出発させてくれ」
「ジャック……返事をしろ……彼女にまたあったのか?」
「うん……」――彼は思い惑った――「ツールーズへ戻る途中に、もういちど彼女に会いに寄り道をしたのだ……」
そして、ジャック・ベルニスはその話を私にしてくれた
第3部第4章(回想ージュヌビエーブとの離別)
この章(あるいは節)は、ベルニスがかつての恋人(人妻の、だから不倫相手の)ジュヌヴィエーヴの家に行くところだが、幻想小説風に描いている。この部分の誤訳については別のところで書いたのでここでは書かない。
Ce n’était pas une petite gare de province, mais une porte dérobée. Elle donnait en apparence sur la campagne. Sous l’œild’un contrôleur paisible on gagnait une route blanche sans mystère, un ruisseau, des églantines. Le chef de gare soignait des roses, l’homme d’équipe feignait de pousser un chariot vide. Sous ces déguisements veillaient trois gardiens d’un monde secret. Le contrôleur tapotait le billet :
– Vous allez de Paris à Toulouse, pourquoi descendez-vous ici ?
– Je continuerai par le train suivant.
Le contrôleur le dévisageait. Il hésitait à lui livrer non une route, un ruisseau, des églantines, mais ce royaume que depuis Merlin on sait pénétrer sous les apparences. Il dut lire enfin en Bernis les trois vertus requises depuis Orphée pour ces voyages : le courage, la jeunesse, l’amour…
– « Passez », dit-il.
長塚隆二訳(ほんの一部だけ手を入れた)
それは田舎の小さな駅ではなくて、忍び戸のようなものだった。見たところ、そこから野原がひらけていた。おとなしそうな改札係の見張る先には変哲もない白い道と小川と野ばらが見えた。駅長はバラの手入れをしているし、駅の人夫がじつは空の手押し車を押すように見せかけていた。こういう変装姿で、秘密の世界の三人の番人が目を光らせていたのだ。
改札係は切符を指でとんとんと突いて、
「パリからツールーズまでですが、どうしてここで下車するのですか?」
「つぎの列車にまた乗るのだがね」
改札係は、彼の顔をじろじろ見つめた。改札係が彼に引き渡すのに二の足を踏んでいるのは、道とか小川とか野原ではなくて、メルラン〔多数の騎士物語に登場する魔法使いの予言者〕以来、忍び込む方法がわかっている外見の下に隠されたあの王国にほかならなかった。それにしても、彼はベルニスの中に、オルフェウス以来この国の旅に必要な、勇気と若さと愛という三つの取柄を読み取ったのにちがいなかった……。
「どうぞ」と彼がいった。
ジュヌヴィエーヴは死の床についている。ベルニスは彼女から永遠に決別せざるを得ない。
彼はそとにでた。不意に声をかけられて呼び戻してもらいたいと無性に願うばかりに、後ろを振り返った。そうなれば、彼の心は悲しみと歓びで身も世もなかろう。けれどもさっぱりだ。何一つ彼を引きとめはしなかった。彼は木立の間を、すいすいとすべりぬけた。それから、垣根をとび越えた。道はかちかちだった。すっかりけりがついたからには、彼は二度とふたたび戻ってはこないだろう。
第3部第5章(ユービ岬から出発)
それから、ベルニスが出発前に、このいきさつの一部始終をかいつまんで話してくれた。「私はジュヌヴィエーヴを、私の世界に連れてこようとしたのさ。私が彼女に見せたものはいっさいがっさい、どんよりして灰色になってしまった。初めての夜から、いい知れぬ厚みがあった。私たちはそれを乗り越えることができなかったのだ。私は彼女に、彼女の家と生活と魂を返すよりほかはなかった。道のポプラの木まで、一本ずつそっくり。われわれがパリへ帰る道すがら、世界とわれわれの間の厚みがへった。まるで、私が彼女を海底に引きずり込もうとでもしたようだ。あとになって、もういちど彼女に追いつこうとしたら、彼女に近づいて手をふれることができた。私たちの間に、空間はなかった。それ以上のものがあったのだ。なんとも説明のしようがない。千年の歳月といったところだ。他人の生活とは、これほどまでにかけ離れているのだ。彼女は自分の白いシーツと、自分の夏と、自分だけの自明の理にしがみつくばかりで、私にはそんな彼女を連れてゆくことができなかったのだ。出発させてくれよ」
(中略)
「ジャック、時間だよ」
こうしてベルニスはユービ岬から出発した。(出発時間の記述はない)
第3部第6章(ポール・エティエンヌからサン=ルイへ)
いまや頭がぼんやりして、彼は夢見心地である。うんと高空から見る地面は、じっと動かないようだ。砂の黄色いサハラ砂漠が、どこまでも続く歩道のような青い海原にはみだしている。腕の立つ職人ベルニスは、右にそれて、横に流れるこの海岸線を、エンジンの軸線に引き戻す。アフリカのカーブにさしかかるそのつど、彼は機械を静かに傾ける。ダカールまでまだ二千キロメートル。
彼の前方には、帰順しない地域の目もさめるほどの白い色。往々にして、岩山はむきだしである。風が砂を吹きはらって、ここかしこにきちんきちんと砂丘ができている。そよともしない空気が、機を母岩のようにすっぽり包んだ。縦にも横にも揺れないし、これほどの高空から見ると、景色もまるきり動かない。風上に向かう機には、時間と持続があるばかりだ。最初の着陸地ポール=エチエンヌ3が記載されているのは、空間ではなくて時間の中で、ベルニスは時計を見つめる。静止と沈黙の時間がなお六時間続いたあと、こんどは蛹からぬけだすように、機体のそとにでるのだ。そこには新しい世界がある。
(中略)
《ポール=エチエンヌヨリ ユービ岬へ 郵便機十六時三十分ニ安着》
《ポール=エチエンヌヨリ サン=ルイヘ 郵便機十六時四十五分ニ出発》
《サン=ルイヨリ ダカールヘ 郵便機十六時四十五分ポール=エチエンヌヲ出発 当方ハ夜間デモ飛行ヲ続ケサセル予定》
郵便機はポール=エチエンヌに到着した後、サン=ルイ4に向けて飛び立った。
Vent d’Est. On décolle de Port-Étienne dans un air calme, presque frais, mais à cent mètres d’altitude on trouve cette coulée de lave.
Et tout de suite :
Température de l’huile : 120.
Température de l’eau : 110.
東風。ポール=エチエンヌを離陸するときの空気は、穏やかで涼しいくらいだが、高度百メートルで、この溶岩流のような熱気に見舞われる。すると、とたんに、
滑温5――百二十。
水温――百十。6
 ところが、ティメリス岬まででると、東風が地面を払うように吹きつけている。もうどこにも逃げ場がない。ゴムの焼ける匂い。磁石発電機か? パッキングだろうか? 回転計の指針がぐらぐらして、回転数が十落ちる。
ところが、ティメリス岬まででると、東風が地面を払うように吹きつけている。もうどこにも逃げ場がない。ゴムの焼ける匂い。磁石発電機か? パッキングだろうか? 回転計の指針がぐらぐらして、回転数が十落ちる。
(中略)
車輪の下十メートルのところを、モーリタニアの砂や塩田や浜辺がさっと流れ去る。砂利が急流となったようだ。
回転数千五百二十。
はじめにエンジンが空回りしたとき、パイロットはげんこつを一発見舞われたような思いである。フランス哨所7まで二十キロメートル。ほかにはない。そこまでたどり着くのだ。
(中略)
風景の突進にブレーキがかかって、それがやむ。こなごなだったこの世界が、もういちど組み立てられる。
サハラ砂漠の中のフランスの小砦。ベルニスを迎えた老軍曹は、同胞にあったのがうれしくて笑い声をたてていた。二十名のセネガル兵が捧げ銃をした。白人ならば、少なくとも軍曹にきまっていた。若ければ、中尉といったところだからである。
「こんにちは、軍曹!」
「ほう! わしの家にいらっしゃい、こんなうれしいことはありません! わしはチェニスの出身でしてね……」
彼の幼少時代、彼の思い出。彼の魂。彼はこれらすべてを一気に、ベルニスにぶちまけた。
(中略)
どこからとも知れず舞いおりてまた飛び立ってゆく若いアイドルを、軍曹はしげしげと見つめる。
……彼に歌を一つと、チェニスと彼自身を思いださせるために舞いおりてきたのだ。これらの美しい使者は、砂漠の向こうのどんな楽園から音もなく舞いおりてくるのだろう?
「さようなら、軍曹!」
「さようなら……」
軍曹は自分自身の気持ちがはかりかねるところから、くちびるを動かすばかりだった。軍曹にすれば、半年分の愛を心にしまっておくのだという術も知らなかったのだろう。
こうして、ベルニスは危ないところを切り抜けてなんとかフランス哨所に着陸し、また離陸することができた。正確な時間の記述は見当たらない。
第3部第7章(郵便機遭難まで)
《セネガルノ サン=ルイヨリ ポール=エチエンヌヘ 郵便機サン=ルイニ未着 至急消息ヲ知ラセヨ》
《ポール=エチエンヌヨリ サン=ルイヘ 当方モ十六時四十五分以降ハ皆目不明 直チニ捜索ニアタル》
《セネガルノ サン=ルイヨリ ポール=エチエンヌヘ 六三二号機七時二十五分ニサン=ルイ発 同機ノ ポール=エチエンヌ着マデ 貴方カラノ出発ハ見合ワセラレタシ》
《ポール=エチエンヌヨリ サン=ルイヘ 六三二号機十三時四十分ニ安着 操縦士カラノ連絡ニヨレバ 視界十分ナルモ皆目見当タラズ 操縦士ノ判断デハ 郵便機ガ規定ノ航路ニアレバ発見デキタハズ 梯形区分捜索ニハ三人目ノ操縦士ガ必要》
《サン=ルイヨリ ポール=エチエンヌヘ 諒解 指令ヲダス》
《サン=ルイヨリ ユービヘ フランス―南米間郵便機消息不明 至急ポール=エチエンヌヘ飛バレタシ》
翌朝になると各地が騒がしくなった。サン=ルイは郵便機が未着だとポール=エティエンヌに問い合わせる。サン=ルイは七時二十五分に捜索機を飛ばす。ポール=エティエンヌでは到着した捜索機のパイロットから郵便機の残骸は見えなかったと報告される。ポール=エティエンヌで2機、ユービからもう1機飛ばすことになる。<私>が搭乗する。
《ユービヨリ ポール=エチエンヌヘ 二三六号機十四時二十分ニ ポール=エチエンヌニ向ケ ユービヲ出発》
(中略)
「きみを待っていたのだ。われわれは日のあるうちに飛べるように、すぐ出発する。一機は海岸の上、もう一機は海岸から二十キロメートル、三番目は五十キロメートルのところを飛ぶ。夜になる関係で、小砦で着陸する。きみは飛行機を替えるかい?」
「うん。バルブがいかれているのでね」
移乗。
出発。
(中略)
私はさんざん探しまわったので、目が疲れている。黒点がとびはねる。もう自分の行く先も五里霧中である。
「それじゃ、軍曹、彼を見たのだね?」
「夜明け方に離陸しましたよ……」
われわれは、小砦のすそに腰をおろす。セネガル兵たちが笑い声をあげ、軍曹は物思いにふけっている。明るいけれども、役には立たないたそがれ。
(中略)
あけぼの。マウル人たちのしゃがれた叫び声。へとへとに疲れきって地面にひざをつく彼らのラクダ。北からこっそりくだってきた兵力三百名のアラビア人匪賊が不意に東に現われて、隊商をみなごろしにしたかもしれないという話だ。
匪賊のほうを探してみたら?
「それじゃ扇形に展開だ、いいね? 中央の機は、真東に進む……」
シムーン〔アフリカなどの砂漠で砂の竜巻を伴う熱風〕。高度五十メートルからはやくも、この風が排気扇のように、われわれをからからにしてしまう。
わが友……。
宝物のありかは、するとここだったのか、さぞきみはそれを探しただろう?
この砂丘の上で腕を組み、くすんだ青い色のあの入江と、星くずのような村々の方を向いたきみは、あの晩はほとんど物の重みがなかった……。
きみが南にくだるにつれて、どれほどのきずながほどけてしまったことだろう。空のベルニスはすでに、もうたった一人の友がいるばかり。一本のくもの糸が、やっときみをつなぎとめているだけだったのだ……。
あの晩、きみはいやさらに重みがなくなるばかりだった。きみはめまいにおそわれた。いちばん真上の星で、宝物が光った。おお、ほんのつかの間だ!
私の友情というクモの糸が、きみをやっとつなぎとめていた。それなのに不実な羊飼いの私は、眠りこんでしまったのにちがいないのだ。
《セネガルノ サン=ルイヨリ ツールーズヘ フランス―南米間郵便機ティメリス東方デ発見サル 付近ニ敵ノ小部隊アリ 操縦士ハ死亡 機体モ破損 郵便物ハ無事 ダカールニ向ケ飛行ヲ続ケル》
第3部第8章(郵便機ダカール着)
《ダカールヨリ ツールーズヘ 郵便物ダカールニ安着》
最後に長塚さんの解説から引用しておこう。
「構成の面でも、この小説はまさにパイロットの周到綿密さを彷彿とさせるものがある。読者はまずはじめに、いくつかの無電連絡によって、なぜともなく郵便機の安否が気遣われる。そのうちに、ベルニスが最後となる任務で飛び立ったとき、彼の心はジュヌヴィエーヴとの不幸な愛の結末と彼女の死という暗い影で曇っていたことがわかる。そのとき、ベルニスの悲劇的な最期が予想されるであろう。周知のように、パイロットのほんのささいな心のわだかまりでも、重大な事故につながるからである。それだからこそ、「操縦士ハ死亡、機体モ破損 郵便物ハ無事」という末尾の電文がいかにも効果的といえよう。この小説の入念な構成は、サン=テグジュペリがあらかじめ航法図で細心に検討した飛行そのものを想起させるのである。」
(この項、終わり)
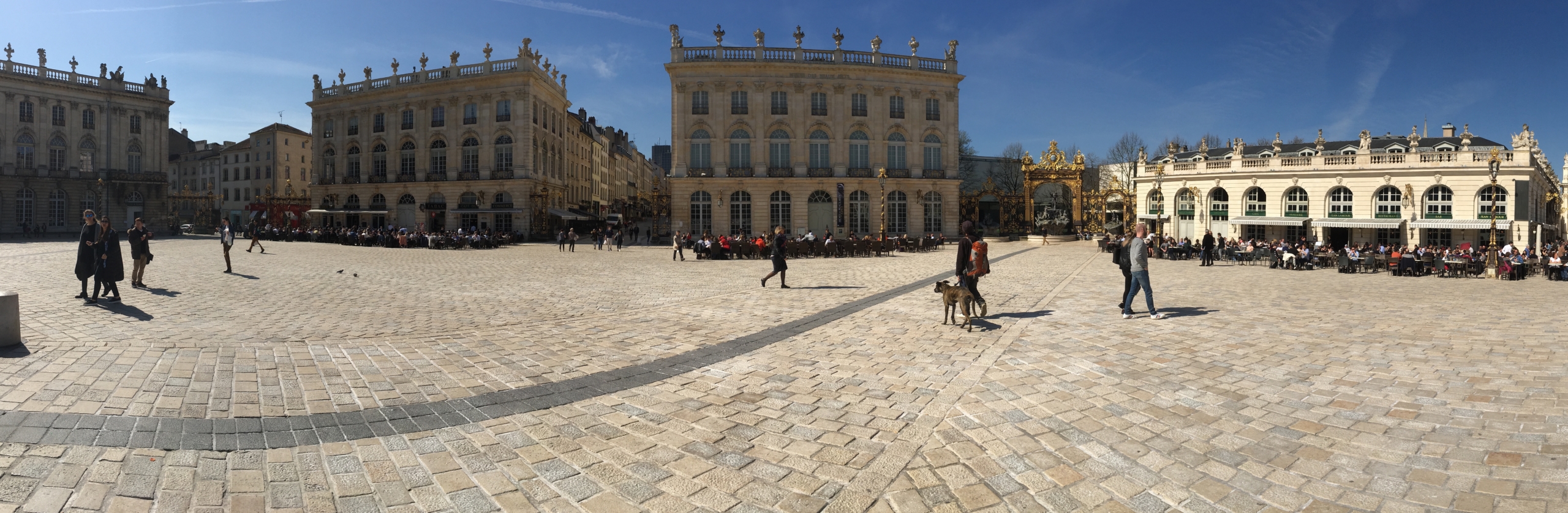







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません